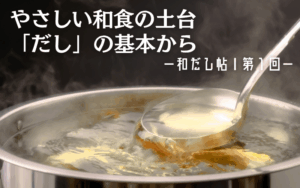和だし帖|うま味と季節をたのしむ台所便り(全5回)
日本の食卓に欠かせない「だし」。
この連載では、だしの引き方や味わい、保存や文化の知恵まで──台所で役立つヒントをお届けします。
少しだけ手間はかかりますが…だしをひく時間は、和食の味を決める大切なひととき。
けれど「せっかく取っただしをどう保存すればいいの?」「出がらしは捨てるしかない?」と迷った経験はありませんか。
ほんの少し工夫すれば、だしは数日〜数週間おいしく使い回すことができ、出がらしも立派なごちそうに生まれ変わります。
今回は、冷蔵・冷凍での保存方法や、出がらしの再活用レシピ、忙しい日に助かる“だし氷”や“だし足し”のコツまでご紹介。
だしを最後まで、無駄なく、おいしく楽しむ知恵をお届けします♪
だしは冷蔵で何日もつ?冷凍はできる?

せっかく丁寧に取っただし、できるだけ長くおいしく使いたいものですね。
ここでは、冷蔵・冷凍の保存期間や、風味を保つためのコツをご紹介します。
一番だし・二番だしの保存目安
- 冷蔵保存:一番だし・二番だしともに2〜3日以内が目安。
- 冷凍保存:1ヶ月程度可能(風味はやや落ちるため、煮物や味噌汁向き)。
冷凍は氷型で小分けにしておくと、必要な分だけ取り出せて便利です。
保存容器の選び方
だしを長持ちさせるには、容器選びが意外にも大切です。用途や保存期間に合わせて容器を選んでみましょう。
- 耐熱ガラス容器:におい移りしにくく、冷蔵・冷凍両対応。
- 製氷皿+保存袋:小分け冷凍に最適。
- 密閉プラスチック容器:軽いが、長期保存はにおい残りに注意。
保存時の注意点
保存の仕方ひとつで、だしの香りや風味は大きく変わります。基本のルールを守って、安心しておいしさを保ちましょう。
- 粗熱を取ってから冷蔵・冷凍へ
- 冷蔵庫は4℃以下、冷凍庫は−18℃以下
- 冷凍はできる限り急速冷凍に(アルミバット使用推奨)
- 解凍は冷蔵庫内か加熱で。常温放置は避ける
二番だし・出がらしの再活用レシピ
だしをとったあとの二番だしや出がらしは、まだまだおいしい力を秘めています。
ほんのひと工夫で、ご飯のお供やおかずに早変わり。
ここでは、日常の食卓で役立つ簡単レシピをご紹介しますね♪
ふりかけ
だしをとった後のかつお節や昆布を、香ばしく炒めて作るご飯のお供。冷蔵で3~4日程度保存できます。
昆布としいたけの佃煮
甘辛く煮詰めた昆布としいたけは、ご飯にもお茶漬けにもぴったり。冷蔵で1週間ほど保存可能。
出がらし昆布入り根菜煮
煮物に出がらし昆布を加えることで、うま味がアップ。野菜の味が引き立ちます。
\「二番だしの引き方」はこちらの記事へ/
▼
二番だしの味噌汁
香りは控えめながらも、しっかりとしたうま味が残る二番だしは味噌汁に最適。
忙しい人におすすめ「だしパック」と「だし氷」

「だしをひく時間が取れない…」「今日は少し面倒だな…」なんていう日もありますよね。
そんなときは、だしパックや冷凍の“だし氷”を活用すれば、短時間でも本格的な風味の料理ができます。
だしパック活用術
毎日だしを引くのは大変…というときに便利なのがだしパック。市販品はもちろん、自家製も意外と簡単に作れます。手軽さと安心感を両立できる方法です。
- 市販だしパック:手軽で失敗が少ない
- 自家製だしパック:かつお節・昆布・干ししいたけを細かくし、ティーバッグに詰めて常備
だし氷
作り置きしただしを「氷」にして保存すれば、必要なときにすぐ使えて便利。忙しい日の味噌汁や煮物も、味が決まりやすくなります。
- 製氷皿にだしを入れて冷凍、固まったら保存袋に移す
- 必要な分だけ味噌汁や煮物に投入可能
- 冷たい麺つゆや和え物にもそのまま使える
味が決まりにくいときの“だし足し”テクニック
「もう少し風味がほしい」「なんとなく味がぼやける」…そんなときの救世主が“だし足し”。料理の途中でも使える、香りとコクを戻す方法をご紹介します。
途中からでも香りを足せる方法
「ちょっと味がぼやけてしまった…」というときでも大丈夫。途中からだしを足すことで、香りや深みをもう一度よみがえらせることができます。
- 追いがつお:削り節を熱湯で30秒煮出し、こして加える
- 濃縮だし:冷凍しただし氷を直接加えて風味を補強
味がぼやけた時のバランス調整
味見をして「物足りない」と感じたら、塩やしょうゆより先に“だし”で整えてみる。こうすることで、塩分を増やさず味の輪郭がはっきりします。
おわりに|日々の台所で生きる、だしの知恵
だしは、一度ひいたらその日のうちに使い切るもの――そう思っている方も多いかもしれません。
けれど、正しい保存方法を知れば、冷蔵や冷凍でおいしさを保ち、忙しい日々の味方に!
出がらしも、ひと工夫でふりかけや佃煮に姿を変え、もう一度食卓を彩ってくれます。
ちょっと意識するだけで、だしはもっと身近に、もっと頼もしい存在になります。
今日の台所に、ぜひ“だしを最後まで使いきる”という小さな習慣を加えてみませんか。
参考文献
- 日本食品科学工学会誌 Vol.62 No.4(2015)「だし成分の経時変化」
- 辻 嘉一『和食の基本』柴田書店
- 農林水産省「食物繊維のはたらき」
- 齋藤 忠夫『昆布の文化誌』成山堂書店
◇だしシリーズ過去記事
◇次回予告
だしは、いつから日本人の心に根付いたのでしょうか。
次回は「うま味」の科学や精進料理・郷土料理とのつながりをたどりながら、だし文化の魅力をひも解きます。
和のこころを感じる一杯が、日々の食卓をさらに豊かにしてくれるはずです。
【和だし帖|うま味と季節をたのしむ台所便り】
(以下の日程で投稿予定です)
第1回:はじめての「だし」入門
第2回:だしの味くらべ 〜素材別で変わる香りとコク〜
第3回:四季のだしごはん 〜春夏秋冬で味わう、だしの魅力〜
第4回:だしの保存と活用術 〜作り置き・冷凍・再利用〜(この記事です)
第5回:だしと和のこころ 〜味覚を育む、だし文化の魅力〜(8/25)