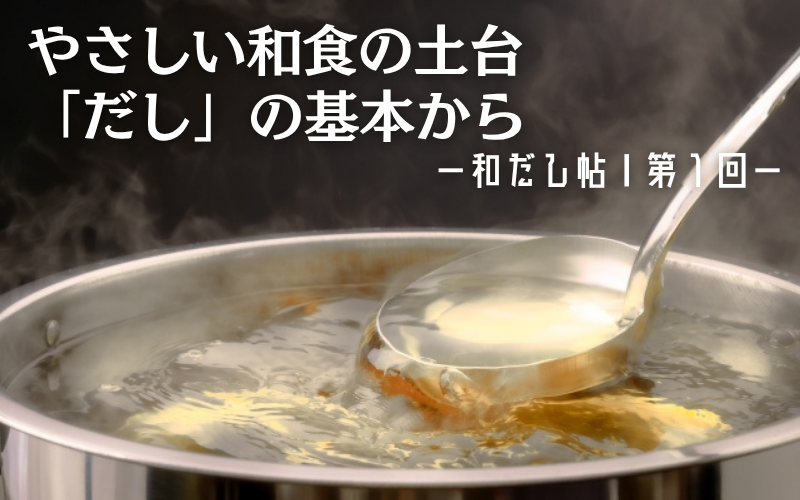和だし帖|うま味と季節をたのしむ台所便り(全5回)
日本の食卓に欠かせない「だし」。
この連載では、だしの引き方や味わい、保存や文化の知恵まで──台所で役立つヒントをお届けします。
こんにちは。「和ごころごはん帖」へようこそ。
今日の台所テーマは、和食に欠かせない“だし”のお話です。
料理好きな方ならもちろんのこと、これから和食に挑戦したい方にも、ぜひ知っておいてほしいのが「だし」のこと。名前は知っていても、実はよくわからない……そんな方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんな「だしビギナーさん」にもわかりやすく、そして「いつも使ってるよ!」という方にも再発見があるような、そんな内容でお届けします。
だしって、そもそも何?

「だし」とは、昆布やかつお節などの素材から、水にうま味を引き出したもの。
たとえば味噌汁、煮物、お吸い物……和食のあらゆる料理に登場する、いわば“縁の下の力持ち”です。
なんとなく味がぼやけてしまう料理も、だしがしっかり効いていると味に輪郭が出て、すっとまとまりがよくなる。それくらい、料理全体を底から支えてくれる存在なのです。
だしに含まれる「うま味」は、甘味・塩味・酸味・苦味に次ぐ、第5の味覚ともいわれています。
特に昆布に多く含まれる「グルタミン酸」、かつお節に含まれる「イノシン酸」など、素材によって異なるうま味成分が含まれていて、これが和食の奥深さをつくっているんですね。
覚えておきたい、基本のだし素材
では、だしをとる素材にはどんなものがあるのでしょうか?
ここでは、家庭でよく使われる代表的な4種類をご紹介します。
昆布(こんぶ)

・やさしく、まろやかな甘みが特徴。口当たりも上品です。
・主な産地:北海道(真昆布、利尻昆布、羅臼昆布など)
・おすすめ料理:お吸い物、湯豆腐、だし巻き卵、精進料理など
昆布だしだけでも十分おいしいですが、かつお節や干し椎茸と合わせることで、より複雑で深みのある味になります。
ちょっと深掘り|昆布の種類、どれがいいの?
昆布にもさまざまな種類がありますが、初心者さんに限らずおすすめなのは「真昆布」か「利尻昆布」。
- 真昆布:甘みと上品なうま味。だしの透明感が特徴。関西で人気。
- 利尻昆布:すっきりとした味わい。お吸い物などにぴったり。
- 羅臼昆布:濃厚でコクが強い。煮物や鍋料理に向いています。
料理や好みに合わせて使い分けると、だしの世界がもっと楽しくなります。
かつお節(鰹節)

・香り高く、力強いうま味が特徴です。
・主な種類:荒節、本枯れ節など
・おすすめ料理:味噌汁、煮物、うどんのつゆなど
グルタミン酸(昆布)とイノシン酸(かつお)のうま味を合わせることで、相乗効果が生まれます。これがいわゆる“合わせだし”です。
煮干し(にぼし/いりこ)

・魚の香ばしさと素朴な味わいが魅力。
・主に使われるのは片口いわし。頭と内臓を取り除いて使うと、えぐみが出にくくなります。
・おすすめ料理:味噌汁、田舎風煮物、郷土料理など
特に九州や四国では、煮干しだしが日常的に使われています。
干し椎茸(しいたけ)

・甘みを含んだ、深いうま味。特に精進料理に欠かせません。
・おすすめ料理:炊き込みご飯、筑前煮、茶碗蒸しなど
干し椎茸に含まれる「グアニル酸」は、昆布と合わせることで抜群の相乗効果を発揮します。
一番だし・二番だしって何が違うの?

「一番だし」と「二番だし」という言葉、耳にしたことはありますか?
これは、使う素材と“だしをとる回数”の違いです。
◎ 一番だし
・昆布やかつお節など、新しい素材でとる1回目のだし
・雑味が少なく、香りが豊か
・主にお吸い物や茶碗蒸しなど、繊細な料理に使います。
一番だしの引き方
◎ 二番だし
・一番だしをとった出がらしの素材を再利用してとるだし
・やや香りは落ちますが、うま味がしっかり出る
・味噌汁や煮物など、しっかり味をつける料理におすすめ
二番だしの引き方
料理によってこの一番と二番を使い分けると、味のバランスがよくなり、素材の無駄も出ません。
忙しい日に頼れる「だしパック」や「液体だし」
「毎日だしをとるのは難しい…」という方も多いと思います。
そんなときは、市販のだしパックや液体だしを取り入れて、無理なく“だし生活”を楽しみましょう。
【選び方のポイント】
・原材料表示をチェック(昆布やかつお節が主原料か)
・無添加や減塩タイプを選ぶと使いやすい
・用途別(味噌汁用、煮物用など)の違いに注意
自然な風味を求めるなら、シンプルな素材だけのものを選ぶのがコツです。
毎日続けたい!かんたん「合わせだし」の作り方
では実際に、ご家庭でも手軽にできる「昆布とかつお節の合わせだし」の取り方をご紹介します。
おわりに|“だし”からはじめる、和ごころの台所

いかがでしたか?
「だしって、難しそう……」そう感じていた方にとって、この記事で少しだけハードルが下がってくださっていたら嬉しいです。
少しの手間はかかりますが、うま味の香りに癒されながら、だしをとる時間は、どこか特別な“台所のひととき”。
素材の声をききながら、ていねいに料理と向き合う。
そんな時間が、和食の根っこにある“やさしさ”なのかもしれません。
次回は「だしの味くらべ」。素材別のだしでどんな風に味が変わるのかご紹介していきます。どうぞお楽しみに。
【和だし帖|うま味と季節をたのしむ台所便り】
(以下の日程で投稿予定です)
第1回:はじめての「だし」入門(この記事です)
第2回:だしの味くらべ 〜素材別で変わる香りとコク〜
第3回:四季のだしごはん 〜春夏秋冬で味わう、だしの魅力〜(8/11)
第4回:だしの保存と活用術 〜作り置き・冷凍・再利用〜(8/18)
第5回:だしと和のこころ 〜味覚を育む、だし文化の魅力〜(8/25)