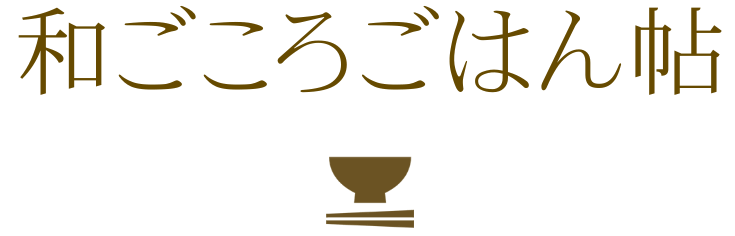和だし帖|うま味と季節をたのしむ台所便り(全5回)
日本の食卓に欠かせない「だし」。
この連載では、だしの引き方や味わい、保存や文化の知恵まで──台所で役立つヒントをお届けします。
朝のお味噌汁をすするとき、煮物の湯気に包まれるとき——
なんだかほっこりと気持ちが癒されるのは、知らないうちに私たちのからだにも心にも染み込んでいる「だし」の存在があるからだと思います。
当たり前すぎて気づかないけれど、実はこのだしが、日本人の暮らしや文化と深く結びついているんです。
最終回となる今回は、“うま味”という科学の視点から、精進料理や郷土料理とのつながり、そして家庭でできる味覚の育て方までをやさしく解説しています。
難しく感じるかもしれませんが、決してそんなことはありません。ちょっと意識を向けるだけで、だしはもっと身近で、もっと楽しく味わえる存在になります。
なぜ日本人に“だし”がしみこむのか?

子どもの頃から慣れ親しんだ味噌汁や煮物。その湯気の奥には、昆布やかつお節のだしが隠れています。
日本人にとって「だしの味」は、特別なごちそうではなく、日々のごはんと共に自然に育まれてきたもの。気づけば、誰もが安心できる“ふるさとの味”として記憶に刻まれています。
このだしの背景には、まず、日本の風土があります。山と海に囲まれ、四季の移ろいが豊かなこの国では、保存食や乾物を活かす知恵が育まれました。
昆布やかつお節、干し椎茸や煮干しといった素材は、保存性だけでなく、深いうま味を与えてくれる貴重な存在。これらを上手に組み合わせ、日常の食事を豊かにしてきたのが「和食文化」の根幹です。
また、日本の家庭料理は「素材の味を活かす」ことを大切にします。
野菜の甘み、魚の香り、豆腐のやわらかさ。これらをそっと引き立て、全体を調和させるのが“だし”の役割でした。だからこそ、だしの存在は無意識のうちに日本人の味覚に刻み込まれていきます。
だしが沁み込むのは舌だけではありません。家族と囲んだ食卓の思い出、体調を崩したときに飲んだ澄まし汁のやさしさ。そんな小さな積み重ねが、「だし=安心の象徴」として、今でも私たちの心に深く息づいています。
「うま味」の正体と科学的背景

「うま味」という言葉は今でこそ世界共通語になりましたが、じつにその研究の始まりは日本にあります。
1908年、東京帝国大学(現在の東京大学)の池田菊苗博士が、昆布の成分から「グルタミン酸」が料理の味を深める働きを持つことを発見しました。これが、世界で五番目の基本味「うま味」として認められるきっかけになったのです。
うま味を生み出す代表的な成分は、大きく分けて3つ。
- グルタミン酸 … 昆布や野菜に多く含まれる
- イノシン酸 … かつお節や煮干し、肉に豊富
- グアニル酸 … 干し椎茸や乾燥きのこに含まれる
この3つは、それぞれ単体でも十分うま味を感じますが、組み合わせると驚くほど相乗効果が生まれます。
たとえば、昆布(グルタミン酸)と鰹節(イノシン酸)を合わせただしが、格別においしく感じられるのはそのためです。科学的には「うま味の相乗効果」と呼ばれ、味覚の奥行きをつくりだしています。
さらに、うま味は「塩分を感じやすくする」性質を持つこともわかっています。だしを使うことで塩の量を控えても満足感を得られるため、和食が世界から“健康的な食文化”と評価される大きな理由にもなっています。
つまり、だしのおいしさは単なる伝統や習慣ではなく、科学的にも裏付けられた「理にかなった味覚」。
古くから日本人が昆布やかつおを組み合わせてきた知恵は、現代の栄養学や食科学に照らしても、きわめて合理的なものだということがわかります。
だしと精進料理・郷土料理とのつながり
日本の食文化において、だしは単なる調味の道具ではなく、祈りや暮らしと深く結びついてきました。
たとえば、寺院で育まれた精進料理。動物性の食材を用いない料理では、昆布や干し椎茸のだしが欠かせませんでした。肉や魚を使わずとも、豊かなうま味を引き出す工夫こそが「精進の知恵」。淡い味わいの中に深みをもたらすだしは、僧侶たちにとっても心を静める大切な存在でした。
一方で、各地の郷土料理にもだしは色濃く息づいています。瀬戸内海沿岸ではいりこだしが親しまれ、東北では干し貝柱やきのこのだしが、九州ではあごだしが日常の味を形づくりました。土地ごとの気候や食材に合わせて「その土地ならではのだし」が受け継がれています。
こうした地域色豊かなだし文化は、「うちの味」「おふくろの味」と呼ばれ、家族の記憶やふるさとへの想いと重なります。精進料理が心の平穏を支え、郷土料理が暮らしを支えるように、だしは日本人の精神と生活を結びつける“見えない絆”として続いてきました。
子どもに伝えたい「だしの味」

子どもにとって、最初に出会う“家庭の味”はとても大切です。
忙しい日々の中で、即席の調味料や加工食品に頼ってしまうことも、もちろんありますが、ほんの少し手間をかけて「だし」を加えるだけで、味わいはぐっとやさしく、豊かになります。
実は子どもの舌は大人よりも敏感で、うま味をしっかり感じ取る力を持っています。そのため、だしの効いたお味噌汁やお吸い物を食卓に並べることは、単に栄養を与えるだけでなく、味覚の土台を育てることにもつながります。
塩分や砂糖に頼らなくても「おいしい」と思える力は、将来の健康にも大きく影響するのです。
また、家族で一緒に「昆布を水に浸けてみよう」「鰹節を削ってみよう」と体験することは、食材への興味や食べる楽しさを育む機会にもなります。食卓を囲んで交わされる会話や、湯気とともに広がる香りは、子どもにとってかけがえのない記憶になるでしょう。
そして、それはきっと大人になってからも心をほっとさせる安心の味。
家庭でのちょっとした工夫や体験を通じて、「だしの味」を子どもたちに伝えていくことができたらいいですね。
家庭でできる“味覚の育て方”

味覚は生まれつき決まるものではなく、日々の食卓の積み重ねによって育まれていきます。特に子どもの時期は、将来の「食の好み」を形づくる大切な時期。家庭で少し意識するだけで、自然と豊かな味覚が育っていきます。
まず大切なのは、だしを活かしたやさしい味付けです。塩や砂糖に頼らず、素材本来の甘みや香りをだしが引き立てることで、五感を通して「食材の味」を覚えることができます。
次に、旬の食材を取り入れること。季節ごとに移り変わる香りや色合いは、自然そのものの教科書。春の菜の花のほろ苦さや、夏野菜の瑞々しさ、秋のきのこの香り、冬の根菜の甘み――こうした味わいを知ることが、感受性を豊かにしてくれます。
また、食べる体験を共有することも欠かせません。台所で昆布を水に浸ける、鰹節を削ってみる、香りを一緒に確かめる――こうした小さな体験が、食への好奇心を育て、「おいしい」という気持ちを強めてくれます。
そして何より、楽しく食卓を囲むことが最大の味覚教育。だしの香りとともに交わされる会話や笑顔は、料理以上の豊かさを子どもにも大人にも届けてくれます。
おわりに|だしがつなぐ、和のこころと食卓
つくづく思うのは、だしというのは、ただの調理のベースではなく、私たちが自然の恵みと向き合い、世代を超えて伝え続けてられてきた和のこころそのものなのだということです。
だしの香りが漂う台所は、それだけでどこか安心できる特別な空間。
料理をしている時間も、「おいしいね」と声を交わすひとときも、わたしたちの食卓をそっと支えてくれています。
決して難しく考えることはなく、毎日使う水のように、自然とわたしたちの暮らしに溶け込んでいるのがだしの魅力です。
そんなだしを、ほんの少し意識して取り入れるだけで、食卓がやさしく、豊かに変わっていきます。
季節ごとに味わいを変えたり、家族の好みに合わせて工夫したり。だしには“正解”がなく、それぞれの家庭に寄り添うかたちがあるのも素敵なところです。
これからも、だしと共にある和の食文化を大切にしながら、日々のごはんを楽しんでいきましょう。
シリーズを読み終えてくださったみなさまへ
全5回にわたる「和だし帖」をお読みいただき、誠にありがとうございました!
昆布やかつお節の基本から、季節ごとの楽しみ方、保存や再活用の工夫、そして文化的な背景まで——だしには奥深い世界が広がっていることを、少しでも感じていただけたら嬉しいです。
だしは決して特別なものではなく、毎日の暮らしにそっと寄り添う存在です。
「今日はちょっとだしを丁寧にひいてみようかな」そんな小さな一歩が、食卓の時間をぐっと豊かにしてくれます。
これからも和食とだしを通じて、四季折々の味わいを大切にしながら、日々のごはん作りを楽しんでいただけますように。
【和だし帖|うま味と季節をたのしむ台所便り】(全5回)
第1回:はじめての「だし」入門
第2回:だしの味くらべ 〜素材別で変わる香りとコク〜
第3回:四季のだしごはん 〜春夏秋冬で味わう、だしの魅力〜
第4回:だしの保存と活用術 〜作り置き・冷凍・再利用〜
第5回:だしと和のこころ 〜味覚を育む、だし文化の魅力〜(この記事です)