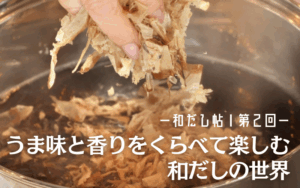~和ごころ素材図鑑~
季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。
そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。
「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。
煮ても焼いても揚げても美味しい!日本の食卓に欠かせない秋冬の定番野菜「かぼちゃ」。普段の食卓だけではなく、郷土料理や行事食としても深く親しまれてきました。
このかぼちゃ、よく考えてみたら「夏に収穫して冬に美味しくなる」不思議な野菜なんですよね。
今回は、かぼちゃの旬・種類・栄養から調理のコツや保存法、和食にぴったりのレシピまで、かぼちゃの魅力を丸ごとご紹介します♪
かぼちゃについての基礎知識

かぼちゃの旬
かぼちゃは「夏に収穫され、秋冬に食べ頃を迎える」少し特殊な野菜です。
- 収穫期:6月下旬〜9月ごろ(夏野菜に分類される)※ミニコラムにて解説
- 食べ頃:収穫直後よりも、1〜2か月追熟させた秋〜冬(10月〜12月)が甘みのピーク
かぼちゃは収穫したてより、保存しておくことでデンプンが糖に変わり、より甘く美味しくなります。
特に冬至の時期(12月22日前後)は、栄養価が高いかぼちゃを食べることで「無病息災」を願う風習が広まりました。
かぼちゃの産地
かぼちゃは全国で栽培されていますが、地域ごとに特徴があります。
主な産地(令和最新統計より)
- 北海道:国内生産の約3割を占める最大産地。特に「えびすかぼちゃ」が有名です。昼夜の寒暖差で糖度が高く、ほくほく食感が特徴。
- 茨城県:関東の大産地。出荷時期が早く、夏場から流通が始まります。
- 長野県:標高差を活かした産地リレーで、初夏〜秋まで長く出荷されます。天ぷらやおやきの具に使われる。
- 鹿児島県・宮崎県:冬春出荷を担い、北海道の端境期を補う。温暖な気候を活かした周年リレー生産の一翼を担っています。
鹿児島では主に 西洋かぼちゃ(えびす・みやこ系) が中心で、ホクホクとした甘みが特徴。
一方、宮崎では伝統野菜の 日向黒皮かぼちゃ(日本かぼちゃ) が有名で、ねっとりした食感と煮崩れしにくさから料亭料理にも重宝されています。
かぼちゃの種類
かぼちゃは大きく分けて 西洋かぼちゃ・日本かぼちゃ・ペポかぼちゃ の3つに分類されます。
それぞれの特徴は次のとおりです。
西洋かぼちゃ(栗かぼちゃ)

日本で最もよく流通しているタイプ。ほくほくと粉質で、甘みが強いのが特徴です。
代表的なのは「えびす」「みやこ」などで、煮物や天ぷら、サラダやスープにも万能。家庭の定番かぼちゃといえばこの種類です。
日本かぼちゃ(黒皮かぼちゃなど)

西洋かぼちゃと違い、さっぱりとしていて、まろやかな甘みときめ細かな舌触りが特徴です。甘さは控えめですが、煮崩れしにくく、だしや調味料の味をよく吸収するため、煮物・含め煮・精進料理などに向いています。
中でも「日向黒皮かぼちゃ(黒皮かぼちゃ)」は日本かぼちゃの代表例として知られ、上品な甘みやなめらかな口当たりで、京都を中心に日本料理の最高級食材として人気があります。
また、京料理に登場するひょうたん型が特徴の「鹿ヶ谷かぼちゃ」も、日本かぼちゃに分類されます。
ペポかぼちゃ

食用から観賞用まで幅広い仲間を含むグループ。夏野菜のズッキーニや、繊維状にほぐれる「そうめんかぼちゃ(金糸瓜)」もペポ種です。ハロウィンのオレンジ色のパンプキンもここに含まれます。
比較的水分が多く、繊維構造がやわらかいものもあり、炒め物・オーブン料理・スイーツなどに使われます。
かぼちゃの栄養
かぼちゃは「冬至に食べると風邪をひかない」と言われるほど、栄養が豊富な野菜です。特にビタミン類や食物繊維が多く、季節の変わり目の体調管理にぴったりです。
- β-カロテン(ビタミンAに変わる成分)
皮や果肉のオレンジ色に多く含まれます。抗酸化作用が強く、免疫力を高め、粘膜や肌を守る働きがあります。油と一緒に摂ると吸収率がアップ。 - ビタミンC
かぼちゃのビタミンCは、でんぷん質に守られているため加熱しても壊れにくいのが特徴。風邪予防や美肌効果に役立ちます。 - ビタミンE
「若返りのビタミン」とも呼ばれ、血流を促し冷え性の改善に期待できます。抗酸化作用で体のサビを防ぐ効果も。 - 食物繊維
腸内環境を整え、便秘解消や生活習慣病予防に効果的。特に皮の部分に多く含まれています。 - カリウム
体内の余分な塩分を排出し、むくみ予防や高血圧対策に。汗をかきやすい夏の栄養補給にも役立ちます。

👉 「皮にも栄養が多い」という特徴は、皮ごと食べる和食の調理法と相性抜群です。天ぷらや煮物では皮ごと調理することで、栄養も見た目の彩りも楽しめますね。
郷土食としてのかぼちゃ

かぼちゃは保存性に優れ、冬場の貴重な栄養源として古くから日本各地で親しまれてきました。土地ごとに独自の食べ方や行事食が伝わり、地域色豊かな料理文化を形づくっています。
冬至のいとこ煮
全国的に広まっているのが「いとこ煮」です。かぼちゃと小豆を一緒に煮る料理で、冬至の日に食べると「風邪をひかない」「無病息災で過ごせる」と言い伝えられています。
小豆とかぼちゃを合わせることで「赤と黄」の彩りになり、祝いの席にもふさわしい縁起物とされました。甘いやさしい味わいが冬の食卓をほっこりとあたためてくれます♪
信州のおやき
長野県の郷土食「おやき」にも、かぼちゃの餡が使われることが多いです。蒸したり焼いたりした皮の中に甘く煮たかぼちゃを包むスタイルで、素朴な甘さが子どもから大人まで人気の定番の具材です。
郷土汁物や郷土麺との相性
甲信地方や山梨では、かぼちゃを「ほうとう」に入れるのが定番。
味噌仕立ての汁にかぼちゃが溶け込むことで、自然な甘みととろみが出て、寒い季節にぴったりの郷土料理になります。信州の「けんちん汁」や「雑煮」の具材としても使われることがあり、冬の食卓に彩りを添えます。
各地の特色ある料理
- 北海道:栽培が盛んなことから、かぼちゃの煮物やスイーツが豊富。郷土菓子「かぼちゃ団子」も有名です。
- 東北地方:保存食文化の一環として、干しかぼちゃやかぼちゃの甘煮が正月料理に登場。
- 九州:温暖な気候を活かして冬場に収穫できるため、雑煮や煮物に使われています。
かぼちゃ調理のコツ

かぼちゃは「ほくほく感」と「甘み」を引き出すことで、いっそう美味しく仕上がります。調理のシーンごとに押さえておきたいポイントをご紹介します。
下ごしらえのコツ
- 硬い皮はレンジで柔らかく
かぼちゃは切るのが大変ですが、電子レンジで軽く加熱すると包丁が入りやすくなります。 - 種とワタはしっかり取る
水分や傷みの原因になるので、スプーンでしっかり取り除くのが基本です。
煮物のコツ
- 面取りをすると煮崩れ防止に
四角い角を軽く落としておくと、美しく仕上がります。 - 皮を下にして煮る
皮の方が固いため、鍋底に皮を向けて並べると形が崩れにくいです。 - 調味料は後から加える
最初はだし汁でやさしく火を通し、最後に調味料を加えると煮崩れしにくく、味もしみやすくなります。
揚げ物・炒め物のコツ
- 油との相性抜群
βカロテンは油と一緒に摂ることで吸収率が上がります。天ぷらやソテーは理にかなった調理法です。 - 厚みをそろえる
天ぷらやフライにするときは5mm前後の厚さに切りそろえると火の通りが均一になります。
蒸し物・スープのコツ
- 蒸すと甘みが増す
蒸気でじっくり加熱するとデンプンが糖化し、自然な甘みが引き立ちます。サラダや離乳食にもおすすめ。 - ポタージュは皮ごと
皮の部分にも栄養が多いため、よく洗って皮ごと加えると彩りも鮮やかになります。
盛り付けのコツ
- 皮を活かす
かぼちゃの濃い緑と果肉の黄色のコントラストは、器の中で季節感を演出してくれます。皮を残すと彩りも栄養もアップ。 - 食べやすい大きさに
煮物はひと口大、天ぷらは少し大きめにすると、見栄えも食感もよくなります。

これらのコツを押さえれば、かぼちゃ料理が格段にレベルアップ!日常の家庭料理はもちろん、おもてなしの席でも自信を持って出せる一皿になりますよ。
かぼちゃの保存方法
かぼちゃは保存性の高い野菜ですが、カットするか丸ごとかで扱い方が変わります。状態に合わせて適切に保存しましょう。
常温保存(丸ごとの場合)
- 保存期間:1〜2か月程度
- 風通しの良い冷暗所で保存。新聞紙で包んでおくと乾燥や傷みを防げます。
- 収穫直後よりも、数週間〜1か月ほど追熟させたほうが甘みが増すのが特徴。

かぼちゃは「夏に収穫して、冬に食べ頃を迎える」不思議な野菜。丸ごとであれば常温保存に最適です。
冷蔵保存(カットした場合)
- 保存期間:4〜7日程度
- 種とワタをしっかり取り除き、ラップでぴったり包んで野菜室へ。
- 水分が出やすいので、キッチンペーパーを敷いて保存すると日持ちが良くなります。

切った瞬間から劣化が始まるので、できるだけ早めに使い切りましょう。
冷凍保存(下ごしらえした場合)
- 保存期間:1か月程度
- 薄切りにして生のまま冷凍、または蒸してマッシュしてから小分け保存もおすすめ。
- 凍ったまま煮物や味噌汁に入れられるので、調理がスムーズ。

離乳食やスープ用には、マッシュして冷凍しておくと便利です。
かぼちゃを使ったおすすめレシピ5選
1. かぼちゃのいとこ煮
冬至の行事食として親しまれる一品。小豆のやさしい甘みとかぼちゃのほっくり感を楽しんでください。
2. かぼちゃの白味噌そぼろあん
やわらかな白味噌と鶏そぼろが絡む、上品でやさしい味わいです。
3. かぼちゃの天ぷら
ほっくりした甘みを衣が包む定番料理。抹茶塩や藻塩を添えると、シンプルながら格別の美味しさです。
4. かぼちゃのごまサラダ
すりごまとしょうゆを加えた和風味のサラダです。ナッツやレーズンでアレンジ自在。
5. かぼちゃの味噌汁
甘みが溶け出す滋味深い汁物。玉ねぎや油揚げと合わせて家庭の味に。
6. かぼちゃの煮物
ほっこりやさしい定番の煮物です。
おわりに|かぼちゃがつなぐ季節と暮らし

かぼちゃは、先人の知恵や暮らしの工夫が息づく野菜です。
夏に収穫されて冬に甘みを増し、行事や郷土料理を通じて人々の健康と団らんを支えてきました。
ほっくりとした甘さは、安心感と、どこか懐かしさを運んでくれますね。
これからの季節、煮物や天ぷら、味噌汁やいとこ煮など、かぼちゃが登場する場面はたくさんあります。
ぜひ日々の台所でも、かぼちゃの彩りとぬくもりを楽しみながら、四季の移ろいを味わってみてください♪
参考文献
- 農林水産省「野菜の旬とかしこい保存方法」
- 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版」
- 『料理物語』(江戸時代の料理書)
👉この記事を読んでくださった方に、さらに楽しんでいただける関連ページをご紹介します。
\和ごころ素材図鑑|栗/
▼

\和だし帖|だしの味くらべ~素材別で変わる香りとコク~/
▼
\和ごはん歳時記|秋の行事食/
▼
\さしすせそ歳時記|砂糖×秋野菜/
▼