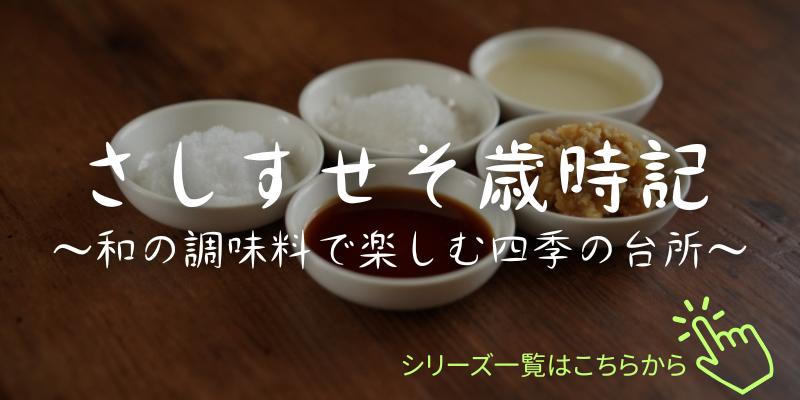~和ごころ素材図鑑~
季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。
そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。
「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。
シャキシャキとした歯ざわり、ほくほくとした甘み。れんこんは、秋から冬にかけて旬を迎える日本の食卓に欠かせない根菜です。
切った断面に並ぶ穴は、どこか愛らしく、昔から「先を見通す」として縁起のよい食材とされてきました。
煮ても、焼いても、揚げてもおいしく、季節の行事にも登場する万能選手。
素朴ながらも、和の台所に深く根づいた存在です。
れんこんの特徴

れんこんは、漢字で書くと「蓮根」…また、根菜類に分類されることから、蓮(ハス)の花の根っこだと思われがちですが、実はハスの地下茎が肥大した部分。
根っこではなく、泥の中に横へと伸びた「茎」の一部です。
切ると見える“穴”は、空気を通すための通気孔。
この構造のおかげで、泥の中でも呼吸ができる仕組みになっています。
見た目の美しさや「先を見通す」に通じる形から、縁起のよい食材とされてきました。
加熱の仕方で変わる「食感」
れんこんの食感は加熱のしかたで大きく変わります。
🔸短時間加熱:シャキシャキと歯ざわりよく
薄切りにして炒めたり揚げたりすると、れんこん特有の軽やかな歯ざわりが生きます。
きんぴらや天ぷらなどに向き、さっぱりとした香りと食感が楽しめます。
🔸じっくり加熱:ほくほく、やわらかく甘みが増す
厚めに切って煮含めると、でんぷんがほぐれ、やさしい甘みと旨みがじんわり。
煮物や筑前煮など、味をしっかり含ませたい料理にぴったりです。
🔸すりおろす:もっちりと粘りが出る
すりおろすことでれんこんのでんぷんとムチン質が混ざり、もちっとした弾力に。
れんこんもちやはさみ揚げ、すまし汁などでやわらかな口当たりを楽しめます。
れんこんの栄養
れんこんには、でんぷん・食物繊維・ビタミンCがバランスよく含まれています。
とくに注目したいのは、加熱しても壊れにくいビタミンC。
れんこんの内部のでんぷんが、熱からビタミンCを守ってくれるため、煮物や炒め物でも効率よく摂ることができます。
また、粘り成分のムチンは、たんぱく質の吸収を助け、胃腸をいたわる働きがあります。
さらに、ポリフェノールの一種であるタンニンには抗酸化作用があり、切り口が黒ずむのはこの成分による自然な反応です。
シャキッと食べても、ほくほく煮ても、栄養がしっかり届く・・・れんこんは、季節の変わり目にうれしい「からだにやさしい根菜」です。
れんこんの旬と産地

れんこんの旬は、晩秋から冬(10月〜翌2月ごろ)。
寒さででんぷんが増し、甘みとほくほく感がいちばん引き立つ時期です。
日本各地で栽培されていますが、地域によって味わいや食感が少しずつ異なります。
れんこんの産地と特徴
🪷全国主要産地まとめ
| 産地 | シェア | 主なブランド | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 約45% | 行方れんこん・小美玉れんこん | 肉厚で粘り強く、煮物に最適 |
| 徳島県 | 約13% | 鳴門れんこん | シャキシャキ食感、炒め物向き |
| 佐賀県 | 約11% | 白石れんこん | やわらかく上品、料亭御用達 |
| 愛知県 | 約10% | 立田れんこん | みずみずしく、天ぷらにも◎ |
| 石川県 | 約5% | 加賀れんこん | 粘りが強く、すりおろし料理に最適 |
※シェア数値はおおよその目安です。
参考元: 農林水産省「作物統計(令和4年/2022年)」、地域別農産物ブランドサイト(茨城県・徳島県・佐賀県・愛知県・石川県各公式HP)より作成。
◆茨城県|霞ヶ浦れんこん
全国シェア約45%を占める日本一の産地。
霞ヶ浦周辺の泥深い土壌で育つれんこんは、肉厚で粘りが強く、煮崩れしにくいのが特長です。
「行方れんこん」「小美玉れんこん」などのブランドが知られ、白く美しい断面が持ち味です。
◆徳島県|鳴門れんこん
吉野川流域で栽培され、全国シェア約13%。
早堀りの“夏れんこん”も多く出荷され、シャキシャキとした歯ざわりが人気です。
炒め物やきんぴらなど、食感を生かす料理にぴったり。
◆佐賀県|白石れんこん
白石平野の粘土質の土壌で育ち、やわらかく上品な口当たり。
全国シェア約11%で、「白石れんこん」として知られます。
煮物やおせちに向く、繊維の細かいなめらかな食感が特徴です。
◆愛知県|立田れんこん
愛西市(旧・立田村)周辺は「蓮根街道」と呼ばれる名産地。
「立田れんこん」はやや細身でみずみずしく、炒め物や天ぷらに合います。
寒さを経ると甘みが増し、煮物にも使いやすくなります。
◆石川県|加賀れんこん
金沢市周辺で栽培される加賀野菜のひとつ。
でんぷん質が多く、すりおろすと強い粘りが出ます。
「れんこんもち」「れんこん蒸し」など、郷土料理に欠かせません。
◆その他の地域
熊本県、岡山県、千葉県などでも生産され、地域ごとに特徴があります。
信州など寒冷地では主に秋冬に各地から入荷し、冬の煮物やおせちの定番として親しまれています。

どれも同じだと思われがちなれんこんも、土の違い、水の違いで表情もさまざま。
料理の用途に合わせて産地を選んでみるのも、楽しいですね。
れんこんの選び方

れんこんを選ぶときの目安にするのは、みずみずしさとハリです!
- 皮の色:全体に淡いベージュで、黒ずみが少ないもの
- 切り口:白くなめらかで、穴の中がきれい
- 節の間隔:短すぎず、ほどよく太いものが使いやすい
カットれんこんを選ぶ場合は、切り口が乾いていないもの、黒ずんでいないものを。
節ごとに売られている場合は、先端よりも「中央部分(中節)」が食感のバランスがよく、煮物や揚げ物に向きます。

保存する際は、泥つきのままなら新聞紙に包んで冷暗所で1週間ほど。
カットしたものは酢水に浸して冷蔵保存し、早めに使い切りましょう。

れんこんは、見た目の素朴さとは裏腹に、とても変化に富んだ野菜ですね。
下ごしらえと調理のコツ
れんこんは、料理によって食感の仕上げ方を変えるのがポイント。切り方や下処理で仕上がりが大きく変わりますので、普段のお料理で、少しだけ意識してみてください。
アク抜きは「酢水」が基本
切ったれんこんは、時間が経つと黒っぽく変色します。
これはポリフェノール(タンニン)の自然な反応ですが、白く仕上げたい場合は酢水(約1〜2%)に5〜10分ほどさらすとよいでしょう。
ただし、長く漬けすぎるとシャキシャキ感が抜けてしまうので注意。
切り方で変わる食感
- 薄切り:火が通りやすく、シャキッとした歯ざわり。きんぴらや酢の物に。
- 乱切り・輪切り(厚め):ほくほく感が出て、煮物や炒め煮に向く。
- すりおろし:粘りが出て、れんこんもち・はさみ揚げ・すまし汁などに。
加熱時間で仕上がりを調整
- 短時間加熱(炒め物・天ぷら):シャキシャキ、爽やかな香り。
- 長時間加熱(煮物・汁物):ほくっとやさしい甘みが引き立つ。
れんこんの持つでんぷんと粘り成分が、火の通り具合で変化します。
「今日は食感を楽しみたい」「ほっこり煮たい」といった目的に合わせて調理すると、いつもの料理がぐっと上達します。
すりおろし活用で格上げ
すりおろしたれんこんは、つなぎにも使えます。
鶏つくねに混ぜればふんわり、揚げ物にすればもっちり。
寒い日には、すりおろしれんこんを加えたすまし汁や葛仕立ての吸い物もおすすめです。

切り方ひとつで「シャキ」「ほく」「もち」。
れんこんの魅力は、まさに“変幻自在の食感”にあります。
れんこんと行事

れんこんは、穴のあるその見た目から、昔から「見通しのよい縁起物」として、祝い膳やおせちに欠かせない食材です。
おせち料理に込められた意味
れんこんの穴は先が見えることから、「将来の見通しが明るい」「先を見通す」という願いが込められています。
おせちの中では、紅白なますと並ぶ「れんこんの甘酢漬け」や、筑前煮の具として登場します。
特に年の初めにいただくことで、1年を見通す縁起担ぎとされてきました。
季節の煮物や精進料理にも
秋冬の献立では、「れんこんのはさみ揚げ」「れんこんのきんぴら」などにも登場。
穴のある形は、素材どうしを結び合わせる“つなぎ役”としても象徴的です。
お盆や法要の席では、輪切りれんこんを使った煮物や天ぷらが供されることもあり、
祝いにも、供養にも使われる“節目の野菜”として日本の食文化に根づいています。
れんこんの保存方法
れんこんは、乾燥と酸化を防ぐことが長持ちのコツ。購入後は状態に応じて、次のように保存しましょう。
泥つきの場合
新聞紙に包んで、冷暗所または冷蔵庫の野菜室で保存。
湿り気を保てば、1週間ほど日持ちします。
泥を洗い落とすと傷みやすくなるため、使う直前に洗うのがおすすめです。
カットれんこんの場合
切り口が空気に触れると黒ずむため、酢水(1〜2%)に浸して冷蔵。2〜3日を目安に使い切りましょう。
密閉容器に入れると乾燥を防げます。
冷凍保存
・生のまま:皮をむいて酢水にさっとくぐらせ、薄切りまたは乱切りにして冷凍。
・加熱してから:軽くゆでて冷凍すると、食感がより保たれます。
どちらも約2〜3週間を目安に。
凍ったまま煮物や炒め物に使えます。

泥つきは「眠ったまま」、カットは「ひと手間で」。
れんこんの保存は、素材の呼吸を守るように扱うのがポイントです。
おすすめ♪れんこんレシピ
れんこんは、主菜にも副菜にも、そしてお祝いの席にも活躍する万能食材です。
季節に合わせて、れんこんの魅力を生かした5つの定番料理を紹介します。
定番の煮物『れんこんの旨煮』
だしのうま味とれんこんのほくほく感が広がる、素朴な常備菜。
香ばしい炒め物『れんこんのきんぴら』
シャキッとした歯ざわりと香ばしい香りがご飯によく合います。
行事にもぴったり『れんこんのはさみ揚げ』
外はカリッと、中はふんわり。お祝い膳にもおすすめの一品です。
冬のほっこり汁もの『れんこんもちのすまし汁』
もちもち食感がやさしい、冬のあたたかい汁ものです。
彩りの一品『れんこんの甘酢漬け』
白と紅のコントラストが美しく、おせちやお祝い膳にぴったり。
🌿おわりに|やさしい願いをのせて
れんこんに限らず、食材を上手に扱うコツは、ちょっとした意識の積み重ね。
切り方や火の通し方を変えてみる…その一工夫が、いつもの料理をぐっと豊かにしてくれます。
シャキッと炒めて元気を出す日、ほくほく煮込んで心を休めたい日。
食感をたのしみながら、れんこんの魅力をいろいろな料理で味わってみてください。
穴のあるれんこんは「見通しのよい縁起物」。
日ごろの食卓にも、ちょっとした願いを添えながら、これからの季節の台所を楽しんでいきましょう♪
\こちらもオススメ♪秋冬野菜/
▼