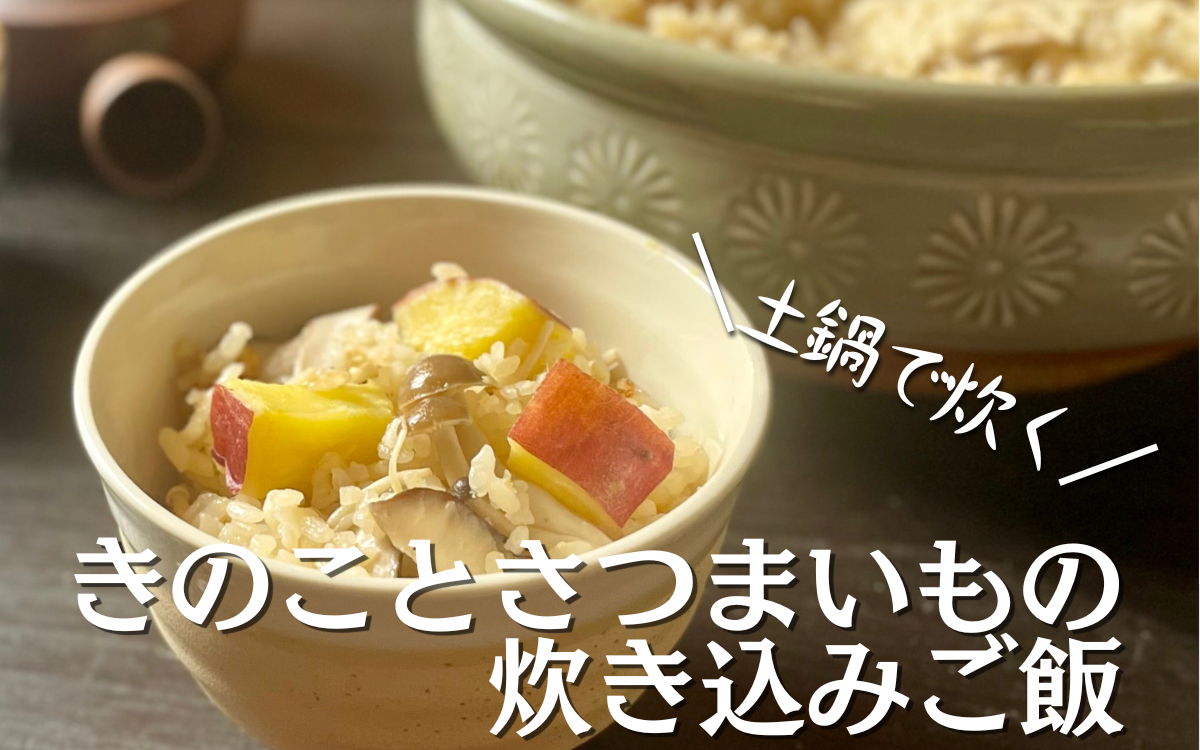~和ごはん歳時記~
季節がひとつ動くたびに、台所にも小さな変化が訪れます。
昔から受け継がれてきた行事や、その日に食べたい和のおかずたち——そんな“季節のしるし”を、日々のごはんといっしょに楽しんでみませんか。
「和ごはん歳時記」では、その月らしい習わしや、心ほっとする和のごはんをやさしくお届けします。季節の台所に、そっと寄り添うことができますように。
12月は、一年の締めくくりにあたる月。冬至を境に日が少しずつ長くなり、古くから人々は「太陽がよみがえる」として無病息災を祈る行事を重ねてきました。
年の瀬には、そばを食べて厄を払う「年越しそば」、新しい年を迎えるための「おせちの仕込み」など、食を通して季節と向き合う時間が続きます。
冬至から大晦日までの行事食をたどりながら、一年を感謝で締めくくる師走の台所の、参考にしていただけたら嬉しいです♪
12月の行事食カレンダー(2025年)
| 日付 | 行事 | 内容・食の風習 |
|---|---|---|
| 12月8日 | 事納(ことおさめ) | 一年の仕事を締めくくる日。神様への感謝を伝える。 |
| 12月13日 | 正月事始め | 正月を迎える準備を始める。 |
| 12月22日 | 冬至 | かぼちゃ ・ゆず湯で「一陽来復」。 |
| 12月24・25日 | クリスマスイブ・ クリスマス | 和のごちそうで楽しむ現代行事。 |
| 12月下旬 | 餅つき | 正月を迎える準備。新米の恵みを分かち合う。 |
| 12月31日 | 大みそか/年越し | 年越しそばで「長寿」や「厄落とし」を願う。 |

行事ごとに追われながらも、台所に立つ時間だけは丁寧にしたいな~と感じる今日この頃です。
各行事の意味と食文化
事納め(ことおさめ)

- 時期:12月8日または13日(地域によって異なる)
- 意味・由来:
1年の仕事や行事を納め、年神様を迎える準備を始める日。
「正月事始め」とも呼ばれ、家の掃除やおせちの仕込みが始まる節目です。
旧暦では、2月8日と12月8日を「事八日(ことようか)」と呼び、どちらか一方を「事始め」、もう一方を「事納め」とする習わしが全国的に定着しています。
2月は農作業や年中行事の“始まり”、12月はその“締めくくり”を意味し、自然の循環に合わせて暮らしてきた日本人の生活の知恵が息づいています。 - 食文化:
この日は感謝を込めた「年取りの膳」を囲む風習があります。
出世魚の鰤や、冬野菜を使った味噌汁など、力を養う料理が並びます。
🫕行事食|お事汁(六質汁)の作り方(一例)
お事汁は、冬野菜を中心とした精進の味噌汁。
大根、にんじん、ごぼう、里芋、こんにゃく、小豆を合わせて“六つの実”とし、
一年の厄を祓い、来年の健康を願う「福招きの汁もの」です。
お事汁のつくり方の一例
- 大根・にんじん・ごぼう・里芋・こんにゃくを食べやすい大きさに切り、下ゆでする。
- 鍋にだしを入れて具材を煮る。
- 柔らかくなったら茹で小豆を加え、味噌で味をととのえる。
- 器に盛り、青ねぎを添える。
詳しい作り方はこちらの記事へ👇

各地でいろいろな言い伝えがあるようですが、お事汁で、一年の厄を祓って新しい年を迎える――。
体も心も温まる、味噌の効いたほっこり汁物がこの季節には似合いますね。
正月事始め(しょうがつことはじめ)
- 時期:12月13日(地域により異なる)
- 意味・由来:
新年の神様「年神様(としがみさま)」を迎えるための準備を始める日。
この日から本格的にお正月の支度が始まり、門松やしめ縄を作ったり、餅つきをしたりと、年越しの準備に取りかかります。
古くは、12月13日を「鬼宿日(きしゅくにち)」と呼び、“婚礼以外のすべてに吉”とされる日であったことから、この日を事始めと定めたともいわれます。 - 食文化:
この日は「煤払い(すすはらい)」や「松迎え(門松の準備)」など、清めと祈りの行事が中心。
特別な料理をするというよりも、台所を清め、年神様を迎える心を整える日とされています。
このころから、おせち料理やお餅の仕込みが少しずつ始まります。
👇お節料理の記事はこちらへ
お歳暮

- 時期:12月上旬〜中旬ごろ(関東では12月初旬、関西では12月13日〜20日頃が目安)
- 意味・由来:
一年の感謝を込めて、お世話になった人へ贈り物を届ける風習。もともとはお正月に先祖の霊へお供えする「御霊祭(みたままつり)」の供物を、親類や師匠などに分け届けたことが始まりとされています。 - 食文化:
お歳暮の品には「日持ちするもの」「家族で分けられるもの」が選ばれ、かつては塩鮭・数の子・するめ・干物などの保存性の高い食材が中心でした。
現代では、ハムや油、調味料など、暮らしを支える“台所の贈り物”として受け継がれています。
冬至|12月22日

- 時期:12月21日頃(2025年は12月22日)
- 意味・由来:
一年で最も昼が短く、夜が長い日。
陰が極まり、再び陽に転ずる「一陽来復」として、運気上昇を願う節目です。 - 食文化:
「ゆず湯」に入り、「かぼちゃ(なんきん)」を食べて邪気を祓う風習があります。また、“ん”のつく食べ物を食べると「運」が呼び込まれるともいわれています。
🫕献立例|冬至の一汁三菜
- 主菜:ぶりの照り焼き
- 副菜:かぼちゃのいとこ煮
- 副菜:春菊とえのきの白和え
- 汁物:ゆずの香りの澄まし汁
- ご飯:五穀ごはん
→ 冬至の運盛り野菜「かぼちゃ」について詳しく見る。
クリスマスイブ・クリスマス

- 時期:12月24・25日
- 意味・由来:
キリストの誕生を祝う祭りであり、西洋では一年の中でも特別な「感謝と祝福の日」。人々が家族や友人と集まり、いのちの恵みや平和への祈りを分かち合う日とされています。
日本では宗教的な意味合いよりも、家族や大切な人と食卓を囲む日として親しまれています。 - 食文化:
チキンやケーキが定番ですが、和食の食卓でも旬の食材を使った“和のクリスマス”もオススメ♪
照り焼きや根菜料理など、彩りと温もりのある料理を並べて、冬のごちそうを楽しみます。
クリスマスの献立例
- 主食:ゆずピラフ風ごはん
- 主菜:鶏もも肉の照り焼き
- 副菜:彩り根菜の白和え
- 汁物:豆乳仕立てのスープ
- 甘味:抹茶のティラミス
餅つき|12月28日頃
- 時期:12月下旬(地域によっては28日頃)
- 意味・由来:
新しい年を迎えるための準備行事。
もち米を蒸してつき、神棚や仏壇に供えることで、年神様への感謝と祈りを表します。 - 食文化:
つきたての餅をみんなで分け合い、無病息災を願います。
「鏡餅」や「のし餅」を作る地域も多く、家族総出の年末行事です。
🫕献立例|餅つきの日の温かい昼餉(ひるげ)
- 主菜:けんちん汁(根菜と豆腐の滋味豊かな汁)
- 副菜:白菜の浅漬け
- 副菜:小松菜のからし和え
- 主食:つきたての丸餅(あんこ・きなこ・大根おろしで)

もうだいぶ昔の話になりますが、幼少のころは庭先で行う餅つきが家族の一大行事でした。出来上がるつきたてのお餅もさることながら、その前に、かまどで蒸したおこわをつまむのが大好きでした。「そんなに食ったらモチにする分がなくなるに」と言っていた、今は亡き祖母の姿が懐かしく思い出されます…
大みそか・年越し
- 時期:12月31日
- 意味・由来:
一年の終わりの日。
「おおつごもり」とも呼ばれ、心身の穢れを祓い、新しい年を迎える準備を整える日です。 - 食文化:
年越しそばを食べて「長寿」や「厄落とし」を願います。
そばは切れやすいことから“厄を断ち切る”ともいわれています。
献立例
- 主食:年越しそば(天ぷら・にしん・鴨南蛮など)
- 主菜:だし巻き卵
- 副菜:ほうれん草のおひたし
- 汁物:そばつゆ(かつおだし)
- 甘味:黒豆の茶巾しぼり
12月に旬を迎える食材とおすすめ料理
| 食材 | 特徴 | おすすめ料理 |
|---|---|---|
| 大根 | 冬の代表根菜。甘みとみずみずしさ。 | ふろふき大根/おでん |
| れんこん | 「見通しがよい」縁起食。 | れんこんきんぴら |
| 柚子 | 冬至や正月に香りを添える。 | ゆず味噌和え/ゆず茶 |
| 鰤 | 出世魚として年末のごちそうに。 | 鰤大根 /照り焼き |
| 白菜 | 鍋や漬物に重宝。冬の保存野菜。 | 白菜と豚肉の重ね蒸し |
| ごぼう | 根深く、家の繁栄を象徴。 | たたきごぼう/きんぴら |
お正月準備と祝い肴のはじまり
12月下旬、台所ではおせちの支度が始まります。
黒豆を煮て、昆布を結び、田作りを干す――
それぞれに「まめに暮らす」「よろこぶ」「五穀豊穣」などの願いが込められています。
おせちは、年神様へのお供えであり、新年最初の“食の祈り”。
素材ひとつひとつに意味があることを知ると、台所の手仕事がぐっと楽しくなります。
代表的なおせち料理
- 黒豆の蜜煮
- 田作り(ごまめ)
- 数の子の味付け
- 昆布巻き
- 紅白なます
- 伊達巻き
- 栗きんとん
など
すべて手作りするのは大変ですが、できるところから少しずつチャレンジしてみるのもいいものです。
\おすすめ記事♪お節料理の意味と由来/
▼
おわりに|行事食で締めくくる、あたたかな年の瀬
一年の終わりを感じる12月。
忙しさの中にも、家族で食卓を囲む時間がほっと心を和ませてくれます。
行事食は、単なる習慣ではなく“暮らしを整える知恵”。
こんにゃくで体を清め、かぼちゃで元気を補い、お餅やそばで新しい年へ願いをつなぐ——
そうした積み重ねが、私たちの心と身体を支えてきました。
どうぞ今月も、季節の食材とともにあたたかな食卓を。
そして、新しい年も健やかに迎えられますように。
参考文献
- 農林水産省「日本の食文化と年中行事」
- 国立国会図書館デジタルコレクション『年中行事事典』
- 各地観光協会公式サイト(京都市観光協会・全国餅組合 ほか)
- 『和食文化事典』(柴田書店)
- 長野県文化財保護協会「伊那谷におけるコト八日伝承に関する調査報告」
\和ごはん歳時記|季節の行事と食の歳時をめぐる/
▼
\11月の行事食はこちら/
▼
\オススメ♪レシピ記事/
▼