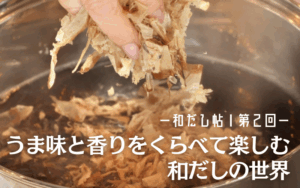~和ごころ素材図鑑~
季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。
そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。
「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。
夏から秋にかけて、八百屋さんの店先で、赤紫の茎の束を見かけたことはありませんか?
それが「芋茎(ずいき)」です。
ずいきは、里芋や八つ頭などの葉柄(ようへい)、つまり葉と茎の間の部分を食べる野菜。
見た目はちょっと地味ですが、シャキッとした歯ごたえと、だしをよく含む独特の食感が魅力です。
名前は知っていても、どうやって食べるのか、どんな料理に使うのか——
そんな方も多いのではないでしょうか。
今回は、この「芋茎(ずいき)」について、やさしくひもといていきます。
芋茎とは|里芋の「茎」をいただく知恵
「芋茎(ずいき)」とは、八つ頭や唐の芋、赤芽芋など、様々な里芋の葉柄を指す言葉。
「茎」と書かれていますが、植物学的には「葉柄」にあたります。
主な種類と特徴
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 赤ずいき(紅ずいき) | 赤紫色。シャキッとした食感で、味がよく染みる。加賀野菜としても知られます。 |
| 白ずいき(軟白ずいき) | 色が白く、やわらかく上品な味わい。奈良や京都などでよく食べられます。 |
| 青ずいき(はす芋系) | 緑がかった茎で、南の地域では「リュウキュウ」と呼ばれることも。 |
地方によって呼び方もさまざまで、干して保存したものは「芋がら」「干しずいき」と呼ばれます。
季節と産地
芋茎(ずいき)の旬は?
ずいきの旬は、6月から9月ごろ。
梅雨明けの頃にみずみずしい赤ずいきが出回り、真夏の盛りには軟白ずいきや青ずいきも市場に姿を見せます。
お盆を過ぎるころには、乾燥させた「芋がら」が登場し、秋から冬にかけての保存食として重宝されてきました。
ずいきは地方ごとに出荷時期がずれ、初夏から初秋までリレーのように旬がつながるのも特徴です。
みずみずしい生ずいきは煮物や酢の物に、秋の深まりとともに干しずいき(芋がら)へと姿を変え、季節の移ろいを感じさせてくれます。
芋茎の産地と郷土料理

ずいきは全国で広く栽培されていますが、地域ごとに品種や色合い、食文化が異なるのが魅力です。
ここでは北から南へ、代表的な産地の特徴をご紹介します。
新潟県

新潟では、里芋の一種「八つ頭」から採れる赤ずいきが中心。
信濃川流域の肥沃な土壌と朝晩の寒暖差が、色づきのよい茎を育てます。
夏の出荷期を終えると、農家では干して「芋がら」として保存する習慣があり、冬の煮物に欠かせない存在です。
雪国ならではの保存の知恵が、今も受け継がれています。
富山県
富山県では、赤ずいきを酢で和えた「酢ずき」が郷土料理として親しまれています。
下ゆでしたずいきを酢と砂糖で軽く味つけするだけの素朴な料理で、赤紫色が鮮やかに発色します。
暑い時季の食卓に涼を添える一品で、お盆や法要の料理にも登場します。
石川県(金沢地域)
加賀野菜のひとつ「加賀赤ずいき」が有名。
八つ頭の仲間から採れる赤紫色の茎で、やわらかく風味豊か。
金沢では夏から初秋にかけて出荷され、京料理や精進料理にも多く用いられます。
見た目の美しさと繊細な味わいが、加賀の食文化を象徴しています。
福井県(奥越地域)

福井県奥越地方では、里芋の茎(赤ずいき)を使った精進料理「すこ」が伝統として残ります。
8〜9月に収穫された赤ずいきを干して保存し、法事や報恩講などの行事で酢漬けとして供されます。
酢に漬けると赤ずいきの色が鮮やかに発色し、古くから「血の巡りをよくする」といった言い伝えもあります。
奥越の冷涼な気候と水田文化が育んだ、北陸ならではの味わいです。
奈良県
伝統野菜の「軟白ずいき(白ずいき)」が栽培され、日光を遮って育てるため色白で繊細な食感に。
奈良盆地の豊かな水と湿潤な気候が、やわらかな茎を育てます。
お盆や法要の料理として、煮物や酢の物に登場することも多く、京・大和の精進文化と深く結びついた食材です。
京都府
京都では、夏から秋にかけて出回る白ずいきを使った煮物「芋茎のたいたん」が定番。
薄味のだしでふっくらと炊き、油揚げを合わせた上品な味わいです。
京料理らしく、色・香り・歯ざわりを大切にした穏やかな煮物で、精進料理にも欠かせません。
大阪府
大阪では、赤ずいきを油揚げとともに炊いた「紅ずいきと油揚げのたいたん」が家庭料理として親しまれています。
しょうゆ・みりん・だしでじっくり煮含めると、ずいきの色がやわらぎ、だしのうま味をたっぷり含んだ一皿に。
夏の終わりを感じさせる定番のおかずです。
徳島県

徳島県では、ずいきを酢で和えた「ずきがし」が伝統的な家庭料理です。
軽くゆでたずいきを、酢・砂糖・醤油・柚子酢(またはすだち酢)で和え、しゃきしゃきとした歯ごたえと爽やかな酸味を楽しみます。
お盆や夏場の常備菜としても親しまれ、柑橘の香りが広がるさっぱりとした味わい。
三重県
関西から東海にかけては、紅ずいきや芸濃ずいきなど、各地で在来種が受け継がれています。
特に三重県津市周辺では「芸濃ずいき」として知られ、家庭料理の定番。
炒め煮や炊き合わせなど、日々の食卓で活躍する親しみのある食材です。
九州・南西地域
温暖な気候を活かして「青ずいき(はす芋)」を栽培。
沖縄や高知などでは「リュウキュウ」と呼ばれ、葉柄専用の品種として独自の食文化を形成しています。
緑がかった茎はアクが少なく、炒め物や吸い物に向くほか、夏の清涼感を楽しむ料理としても親しまれています。
食感と味わい|しゃきしゃき、でもしっとり
ずいきの魅力は、なんといっても独特の食感。
表面はつるんとして軽やか、噛むとシャキッと歯ごたえがあり、すぐに「じゅわっ」とだしがしみ出します。
見た目は地味でも、煮物や酢の物にするとその存在感は抜群。
どんな味付けにも寄り添ってくれる、まさに名脇役の野菜です。
下ごしらえ|少しの手間が美味しさの秘訣
赤ずいきはアクが強く、皮をむくときに手がかゆくなることもあるので、ゴム手袋を使うのが安心です。
下処理の手順
赤ずいきは皮が硬く、アクも強めです。
包丁の先で端を少し切り、皮を引くようにしてむきます。
赤紫色の薄皮をすべて取り除くと、なめらかな食感になります。

むいたずいきは、3〜4cmほどの長さに切ります。
煮物や和え物など、用途に合わせてやや長め・短めに調整してもOKです。
切ったずいきをたっぷりの水に30分ほどさらします。
この工程でアクが抜け、独特のえぐみや苦みが和らぎます。
水が濁ってきたら、途中で一度替えるとより効果的です。

鍋に湯を沸かし、少量の酢(湯1ℓに対して小さじ1程度)を加えて2〜3分ほどさっとゆでます。
アクと変色を防ぎ、きれいな色に仕上がります。
ゆで上がったら冷水に取り、水気を切って調理に使います。


👆ここまで済ませれば、煮物や和え物などにすぐ使えます。
おいしい食べ方レシピ
ずいきは、煮る・和える・炒めるのどれも得意。
味が染みやすいので、だしを活かした優しい味つけがおすすめです。
ここでは定番の芋茎料理を紹介します。
ずいきの煮物
油揚げやにんじんと一緒に、だしでじっくり煮含める定番の一品。芋茎と油揚げを一緒に炊く料理は、大阪や奈良などで郷土料理として親しまれています。
ずいきの酢味噌和え
酢のさっぱり感と味噌のコクが好相性。食欲の落ちやすい季節にもおすすめです。
ずいきの甘辛炒め
しょうゆとみりんで甘辛く炒める、ごはんがすすむおかず。お弁当にも◎。
芋がらの煮付け
乾物の「芋がら」を戻して作る常備菜。素朴なうま味があり、保存性も抜群。

ずいきは、冷めても美味しいのが魅力。
前日に作っておくと、味がよく染みてよりおいしくいただけます。
保存のコツ
生のずいき
新聞紙に包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。
乾燥しやすいので、湿り気を保つように包むのがポイント。
できれば2〜3日以内に使い切ると、しゃきっとした歯ごたえが楽しめます。
長く置くと切り口が黒ずみ、アクが強くなるため早めの調理がおすすめです。
下ゆでしたずいき
下ゆでして冷ましたずいきは、水気をしっかり拭き取り、小分けにして冷凍保存します。
使いやすい分量ごとにラップで包み、フリーザーバッグに入れておくと便利。
自然解凍または電子レンジで軽く温めれば、そのまま煮物や和え物に使えます。
冷凍で約3週間を目安に使い切りましょう。
芋がら(干しずいき)
しっかり乾燥させた芋がらは、湿気の少ない場所で密閉袋や保存瓶に入れて常温保存します。
直射日光を避け、風通しのよい棚や戸棚に置くと長持ちします。
使うときは、ぬるま湯で1時間ほど戻し、柔らかくなったら軽く水洗いしてから煮物などに。
乾物ならではのうま味が、じんわりと広がります。
おわりに|暮らしに残る「季節の知恵」
ずいきは、派手さはないけれど、日本の食文化を静かに支えてきた野菜です。
葉っぱも、茎も、芋も——どの部分も無駄にせず食べつないできた、先人の知恵の象徴。
秋の台所に、ほんの少しだけ手をかけて。
だしを含んだずいきを口にすれば、やさしい季節の味わいが広がります。
\こちらもオススメ♪秋の野菜/
▼
\だしの味くらべ|素材別で変わる香りとコク/
▼