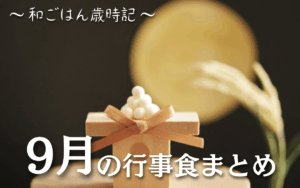~和ごころ素材図鑑~
季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。
そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。
「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。
秋の食卓を彩る食用菊は、鮮やかな色合いと、ちょっと特別な香りや歯ざわりが魅力です。
日常的にはなじみのない方も多いかもしれませんが、実はとても扱いやすい食材。
ゆでて和えるだけなど簡単な調理で、ぐっと季節感を出せるのが嬉しいところです。
「花を食べるなんて少し不思議」と思う方もいるかもしれませんが、昔から健康や長寿を願って食べられてきた歴史ある食材です。
こちらではそんな食用菊の魅力や調理法、そして和食での楽しみ方を、できるだけわかりやすくご紹介しています♪
食用菊とは?

食用菊は、観賞用の菊とは違い、苦みが少なく食べやすいように栽培されている食用の菊です。
食用菊の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 旬 | 9月〜11月(秋) |
| 主な産地 | 山形県・新潟県(全国上位)/愛知県・長野県など |
| 主な品種 | もってのほか(紫〜桃色)/阿房宮(黄色)/寿(淡黄色) |
| 文化的背景 | 重陽の節句に食べられる/東北地方では日常食にも |
| 栄養 | β-カロテン・ビタミンC・カリウム・ポリフェノール(抗酸化作用が豊富) |
食用菊の旬と産地
食用菊の旬は 秋(9月〜11月)。短い期間しか味わえないため、まさに季節限定のごちそうです。特に晩秋には、花びらの色合いや香りがいっそう深まります。
主な産地は 山形県・新潟県。東北地方を中心に、古くからおひたしや酢の物にして、秋の常備菜として日常的に食べる文化が根付いています。
愛知県や長野県などでも栽培され、直売所や市場で手に入ることもあります。
文化的背景
菊は日本では「長寿」「不老不死」を象徴する花。
9月9日の「重陽の節句(菊の節句)」には、菊花酒を飲んだり料理に用いたりして、健康や延命を願う習慣があります。
食用菊の種類
食用菊にはさまざまな品種があり、色や味わいに個性があります。代表的なものがこちら…
もってのほか(山形)/かきのもと(新潟)

正式名称は『延命楽』。
紫〜紅色の花びらが美しく、シャキッとした歯ざわりが特徴。山形では「もってのほか」、新潟では「かきのもと」と呼ばれ、どちらも秋の代表的な食用菊として親しまれています。
名前の由来は地域ごとに異なり、「天皇家の菊を食べるなんてもってのほか」説や、「柿の実が色づく頃に咲く」説など、土地に根ざした呼び方が残っています。
香りが爽やかで人気の高い品種です。名前のとおり「長寿を願う食材」として親しまれてきました。
『阿房宮』(あぼうきゅう/新潟)
鮮やかな黄色の花びらが美しく、料理に加えると食卓が一気に華やぎます。苦みが少なく食べやすいのも魅力です。
『寿』(ことぶき/山形・愛知ほか)

淡い黄色でクセがなく、あっさりとした味わい。和え物や酢の物、汁物の彩りなど幅広く使える万能型。縁起の良い名前から祝いの席にもぴったりです。
食用菊の栄養
食用菊は見た目の美しさだけでなく、栄養価の高さも魅力です。
- β-カロテン:抗酸化作用、皮膚や粘膜を守る
- ビタミンC:免疫サポート、疲労回復
- カリウム:塩分排出、むくみ予防
- ポリフェノール:老化防止、生活習慣病予防
「延命楽」と呼ばれるてきた背景には、こうした健康効果が関係しているのかもしれません。
下処理と調理の基本

きれいな色と食感を活かすために欠かせない下処理です。
- 花びらをほぐし、ガクを取り除く
- 熱湯に塩ひとつまみを加え、30秒〜1分ほどサッとゆでる。
- 冷水にとり、水気をしっかり絞って使う。
おいしくきれいに仕上げるコツ
- 色鮮やかに仕上げるには
ゆでる際に酢をほんの少し加えると、花びらの色が鮮やかに保たれます。 - 茹ですぎないこと
ゆで時間は30秒〜1分ほど。長くゆでると色あせや食感の劣化につながるので注意しましょう。 - しっかり水気を切る
花びらは水分を含みやすいため、よく絞ることで味がぼやけず、和え物も水っぽくなりません。 - 香りを楽しむ食べ方
ポン酢や柚子、すだちなど、柑橘系を合わせると爽やかさが増し、菊の香りを引き立ててくれます。 - 保存の工夫
ゆでて水気を切ったものを冷蔵で2〜3日。冷凍保存する場合は小分けにしてラップに包むと便利です。
食用菊の代表的な料理

食用菊はそのままでは少し扱いにくそうに見えるかもしれませんが、実はとてもシンプルな調理で楽しめる食材です。
さっとゆでて和える、酢に合わせる、衣をつけて揚げるなど、どれも家庭で気軽にできるものばかり。彩りを添えるだけで食卓が一気に秋らしくなるので、普段の献立にも取り入れやすいですよ。
ここでは、食用菊を使った代表的な料理をご紹介します。
菊のおひたし
まずは定番、菊の味わいをいちばんシンプルに楽しむならこれ。
食用菊といえばまずはこれ。さっと湯通しした花びらを、三杯酢や薄口しょうゆで和えるだけ。シャキッとした歯ごたえとほのかな香りが楽しめ、菊そのものの味わいを一番引き立ててくれます。
菊の酢の物
彩りと爽やかさを添える副菜にぴったり。
大根やきゅうり、わかめなどと合わせれば、彩り鮮やかでさっぱりとした副菜に。甘酢や土佐酢を使うと、菊の苦みがやわらぎ、食べやすさが増します。箸休めにぴったり。
菊の天ぷら
香りを引き立て、食卓を華やかにする一皿。
衣を軽くつけて揚げると、花びらの形がそのまま広がり、見た目にも華やか。口に入れるとほろっとほどける食感と、ふんわりとした香りが広がります。塩を少し添えるだけで、上品なおつまみに。
菊花ポン酢
ゆでてポン酢をかけるだけ、手軽に旬を楽しめる料理。
ゆでた花びらにポン酢をかけるだけのシンプルな一品。短時間で作れるのに、秋らしい華やぎが食卓に広がります。大根おろしやしらすを添えると、さらに風味豊かに。
菊ときのこの和え物
秋の味覚同士を合わせた、滋味深い副菜。
舞茸やしめじなど秋のきのこと相性抜群。菊のシャキッとした食感と、きのこのうま味がよく合います。だしじょうゆや柚子酢で和えると、季節感のある副菜に仕上がります。

保存方法
- ゆでて水気を切り、小分けにして冷蔵保存(2〜3日)
- 冷凍も可能(軽くゆでてから小分け冷凍→おひたしや和え物に活用)
👉 彩りが欲しいときにすぐ使えるので、作り置きもおすすめです。
生の食用菊とあしらい・飾りつけについて

食用菊は、料理の彩りを添える「あしらい」としてもよく使われます。特にお造りや盛り合わせの中に、一輪の花や花びらが添えられているのを目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
飾りとしての使い方
- 一輪そのままを器に添える
お刺身や小鉢に添えると、秋らしい彩りが加わります。 - 花びらを散らす
茶碗蒸しやお吸い物の仕上げに散らすと、季節感がぐっと引き立ちます。
よくある誤解Q&A|食用菊をもっと安心して使うために
- お刺身に添えてある菊の花は食べてもいいの?
はい、食用菊なので食べられます。ただしそのままかじるのではなく、花びらを外してしょう油に入れ、お刺身と一緒に味わってみてください。菊の香りと風味を楽しむことができます。
- 生のままサラダに散らしても大丈夫?
はい、大丈夫です。ただ、食用菊には軽いアクや渋みがあるので、たくさんのせるのではなく、彩り程度に散らすのがいいですね。
- 飾りに使った菊はそのまま捨てるしかない?
捨ててしまうのはもったいないです。花びらを取り外し、下ゆでして水気を切れば、おひたしや和え物に再利用できます。見た目の彩りだけでなく、食材として二度楽しめるのも食用菊の魅力です。
- 観賞用の菊と食用菊の違いは?
観賞用の菊は見た目の美しさを重視しており、苦みや農薬の問題から食用には向きません。必ず「食用菊」と表示されたものを選びましょう。
おわりに|秋を彩る小さな花を食卓に

食用菊は、食卓に季節感や華やぎを添えてくれる存在です。ちょっとした副菜に添えるだけでも、食事の雰囲気がぐっと秋らしく変わります。
調理法や使い方も、それほど難しいものではないですね。
スーパーの地場野菜コーナーや、秋の直売所・産直通販でも手に入るので、見つけたら是非手に取ってみてください。
秋の短い季節だけに味わえる贅沢。ぜひ、旬のうちに食卓に取り入れてみてくださいね♪
【参考文献】
\菊花で季節の行事食を楽しむ/
▼