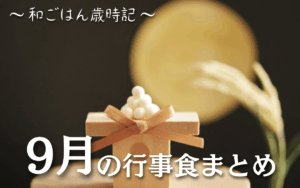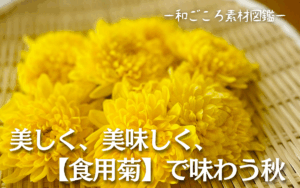霜が降り始め、冬への移り変わりを感じる11月。実りの秋の名残と、冬に備える食材が揃う季節ですね。
11月は、文化の日や七五三、勤労感謝の日など、行事も多く、食卓に季節を取り入れやすい月です。
この記事では、11月ならではの行事食と、旬の食材を使った献立アイデアをご紹介しています。
目次
スポンサーリンク
11月の行事食カレンダー(2025年)
| 日付 | 行事 | 行事食・食材例 |
|---|---|---|
| 10月中旬〜11月上旬(11月2日)(※) | 十三夜(後の月) | 月見団子 、栗 、豆類、月見の供え物/おやつ |
| 11月3日 | 文化の日 | 菊 ・紅葉をあしらった料理 |
| 11月7日 | 立冬 | 大根 ・かぶ 、根菜の料理 |
| 11月15日 | 七五三 | 鯛の塩焼き、千歳飴、紅白の和菓子など |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 感謝を込めたおもてなし料理 |
(※)2025年(令和7年)の十三夜は11月2日です。
近年の十三夜は10月になることが多いため、今年は双方のカレンダーで紹介しています。
スポンサーリンク
各行事の意味と食文化
十三夜(後の月)(2025年は11月2日)
「十三夜(後の月)」は10月になることが多いため、「10月の行事食まとめ」でとりあげています。👇こちらへ
文化の日(11月3日)
- 意味・由来
文化の日(11月3日)は、1946年に日本国憲法が公布された日で、翌年から祝日となりました。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とし、芸術や学問をたたえる式典や展示会などが全国で行われます。
もともとは明治天皇の誕生日(明治節)に由来し、現在も「文化」「芸術」「学び」を象徴する祝日として親しまれています。 - 食文化
文化の日の特別な伝統食はありませんが、ぜひ秋の彩りを食卓に添えてみてください。菊の花をあしらった料理や、紅葉をイメージした盛り付けを添えると、文化的な雰囲気を食卓に演出できます。
立冬(りっとう)(11月7日)
- 時期
立冬は二十四節気のひとつで、2025年は11月7日にあたります。暦のうえで「冬の始まり」とされる節目の日です。 - 意味・由来
「立=はじまる」「冬=寒さの季節」という意味。日照時間が短くなり、朝晩の冷え込みが増す頃。農作業は収穫から冬支度へと移り変わり、保存食づくりも始まります。 - 食文化
立冬には、体をあたためる根菜や豆類を使った料理がよく食べられます。昔から「冬に備えて栄養を蓄える」ことを意識した食習慣があり、旬の大根・かぶ・里芋などを煮含めた料理や、根菜の味噌汁・鍋料理が好まれます。
「立冬」の献立例
- 主食:大根葉ごはん
- 主菜:ぶり大根
- 副菜:かぶのそぼろあんかけ、里芋の煮ころがし
- 汁物:根菜たっぷり味噌汁
- 甘味:柚子ゼリー
七五三(11月15日)

- 意味・由来
子どもの成長を祝う伝統行事。平安時代から「髪置」「袴着」「帯解」など、年齢に応じた節目が祝われていました。 - 食文化・飾り付け
千歳飴を結絵(華やかに包装)し、紅白の和菓子や季節の果物を添えます。
勤労感謝の日(11月23日)
- 意味・由来
労働を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日。 - 食文化
普段よりちょっと手間をかけた「もてなし料理」を出す家庭も。秋の恵みを存分に使った献立で感謝を表します。
スポンサーリンク
11月に旬を迎える食材とおすすめ料理
| 食材 | 特性・旬時期 | 料理例 |
|---|---|---|
| 栗 | 旬は9〜10月。11月は生栗の流通は減るが、氷温保存や加工品で楽しめる。 | 栗ご飯 、栗の渋皮煮 、栗羊羹、栗きんとん、栗の甘露煮 |
| 柿 | 甘味が増し、干し柿も作られる時期 | 柿なます、干し柿、柿と胡麻豆腐、柿と大根のラペ |
| 柚子 | 冬至に向け香りが高まる | 柚子大根、ゆず味噌、ゆず茶 |
| 大根 | 身がしまって甘みが出る | ふろふき大根、ぶり大根 、大根ステーキ |
| かぶ | やわらかく甘みがあり汁物に最適 | かぶのそぼろあん 、かぶの浅漬け |
| さつまいも | 甘さが増し冬の副菜やおやつにぴったり | 大学芋、さつまいもご飯 、いも煮 |
| きのこ類 | 秋の名残を楽しむ | きのこご飯、土瓶蒸し、きのこ汁 |

🌰 栗は9〜10月が旬のピークですが、11月には氷温熟成されたものや、渋皮煮・栗きんとんといった加工品として食卓に上ることが多くなります。『秋の名残を楽しむ味わい』として、まだまだ栗は秋の食卓に季節感を添えてくれます♪
おわりに|行事と旬で暮らしに季節感を
11月は、秋の余韻と冬の足音が入り混じる移行の季節。
行事をきっかけに旬の食材を取り入れ、食卓に季節感を添えてみてください。できるところから少しずつ・・・家族や大切な人とともに、「食」を通して季節を味わう時間を大切にしたいですね。
📚 参考文献
- 国立国会図書館デジタルコレクション『暦便覧』(江戸時代刊)
- 内閣府「国民の祝日について」
- 農林水産省「食べもの暦」
\9月の行事食まとめに戻る/
▼
\食用菊について詳しく知る/
▼
\和の調味料と秋野菜の美味しい関係はこちら/
▼
スポンサーリンク