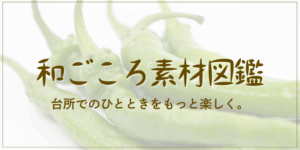~和ごころ素材図鑑~
季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。
そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。
「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。
もしかしたら、食卓にいちばんのぼるのは「鶏肉」なのよね、というご家庭は多いかもしれません。まさしく我が家もそうです。
照り焼き、唐揚げ、親子丼など、「今日はこれにしよう!」と気軽に作れる定番料理が多いですし、なにより昨今の物価高で、安価で手に入る鶏肉のありがたみはヒシヒシと感じています。
現在だけでなく、魚食文化の日本においても、鶏肉は昔から「扱いやすくて食べやすい」存在だったようです。
今回はそんな鶏肉について、歴史や栄養、部位の特徴、和食ならではの調理法などをまとめてご紹介します。
読み進めていただくと、毎日の献立のヒントが見つかるかもしれません。
鶏肉の歴史と食文化

鶏肉が日本でどのように食べられてきたかを、時代ごとに振り返っていきます。
古代〜中世(〜16世紀ごろ)
『古事記』や『日本書紀』において、鶏は時を告げる鳥として登場しますが、食用としての記録は少なく、主に供物や闘鶏に用いられていました。
江戸時代(17〜19世紀前半)
江戸初期には肉食禁止令の影響もあり、鶏肉も制限されていましたが、幕末にかけては薬膳的に「脚気に効く」とされ需要が高まりました。
このころは、鶏肉といえば鴨などの野鳥のことを指し、鶏(にわとり)は卵を採るために庭先で飼われていました。
明治以降(19世紀後半〜20世紀初頭)
文明開化とともに肉食が一般化。養鶏が盛んになり、「かしわ」と呼ばれる鶏肉は国民的な食材となりました。
現代(20世紀後半〜現在)
安価で入手しやすく、牛・豚と並ぶ三大食肉のひとつとなりました。大量生産向けに改良された食肉専用の若鳥(ブロイラー)の普及と並行して、古くからその土地で改良されてきた地鶏も確立していきます。
鹿児島県の薩摩地鶏、愛知県の名古屋コーチン、秋田県の比内地鶏などが有名ですね。
鶏肉の栄養価と健康
鶏肉は「高たんぱく・低脂肪」。部位によって栄養バランスが異なり、健康や美容の強い味方です。
たんぱく質
- 鶏肉は必須アミノ酸をバランスよく含む良質なたんぱく源。
- 筋肉や皮膚、髪の健康を保ち、疲労回復にも役立ちます。
- とくにむね肉・ささみは高たんぱくで低脂肪。運動後の食事やダイエットに最適です。
脂質
- 鶏肉の脂質は比較的少なく、しかも不飽和脂肪酸(オレイン酸・リノール酸)を多く含みます。
- 悪玉コレステロールを下げ、動脈硬化の予防にも効果的といわれます。
- 皮には脂質が集中しているので、カロリーを抑えたいときは除くと良いでしょう。
ビタミン類
- ビタミンB6:アミノ酸代謝を助け、疲労回復や肌荒れ予防に。
- ナイアシン(ビタミンB3):糖質・脂質の代謝をサポートし、エネルギーづくりに欠かせません。
- ビタミンA(レチノール):鶏レバーに豊富で、目や粘膜の健康維持に役立ちます。
ミネラル
- カリウム:余分な塩分を排出し、高血圧予防に。
- リン:骨や歯の健康に必要。
- 鉄分:鶏レバーに豊富で、貧血予防に効果的。
部位ごとの栄養の特徴
- むね肉・ささみ:高たんぱく・低脂肪でヘルシー。
- もも肉:脂質がやや多く、コクとエネルギー補給に向く。
- 皮:脂質が多いが、カリッと焼けば香ばしさが魅力。
- レバー:鉄分・ビタミンAが豊富で栄養価が高い。
健康面での注意点
- 脂肪やカロリーを気にする場合は「皮」を外すのがおすすめ。
- レバーは栄養豊富ですが、ビタミンAが多いので食べ過ぎに注意(週1〜2回程度が目安)。
- 下処理や加熱をしっかり行い、食中毒を防ぐことが大切です。
部位ごとの特徴と使い方

部位によって味わいも調理法も違うのが鶏肉の魅力です。毎日の献立の参考にしてみてください。
- もも肉:旨味たっぷり。煮物や唐揚げに。
- むね肉:淡泊で低脂肪。高たんぱく・低脂肪でダイエットや美容向き。蒸し鶏やサラダに。
- ささみ:むね肉同様、高たんぱく・低脂肪でもっともヘルシー。おひたしや和え物向き。
- 手羽:ゼラチン質豊富。煮込みやスープに。(※後ほど「手羽の種類」を紹介しています)
- ひき肉:つくねやそぼろなど多彩。
鶏肉部位ごとの特徴(1〜5段階評価)
| 部位 | 旨味 | コク | 脂の多さ | あっさり感 | 出汁力 |
|---|---|---|---|---|---|
| もも肉 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| むね肉 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| ささみ | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 手羽 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| ひき肉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
※手羽の種類と特徴
鶏肉の「手羽」は大きく分けて次の3種類があります。
手羽先(てばさき)

手羽の先端にあたる部分で、骨が細く皮が多いのが特徴です。ゼラチン質を多く含み、煮込むとぷるぷるに、揚げるとパリッと香ばしく仕上がります。名古屋名物の「手羽先唐揚げ」などでもよく知られています。
手羽元(てばもと)

手羽の根元にあたる部分で、骨が太く肉厚。煮込み料理やスープに向いており、味がしみ込みやすくジューシーに仕上がります。唐揚げにも人気の部位です。
手羽中(てばなか)

手羽先と手羽元の間にある部分で、「フラット」とも呼ばれます。肉と皮のバランスが良く、比較的食べやすい部位です。塩焼きやから揚げ、甘辛煮など幅広い料理に活躍します。市販では手羽先とまとめて販売されることも多いです。
手羽の種類比較表
| 手羽先 | 骨が細く皮が多い/ゼラチン質が豊富でコラーゲンたっぷり/煮るとぷるぷる、揚げるとパリッと香ばしい | 唐揚げ(名古屋風)、甘辛煮、グリル焼き |
| 手羽元 | 骨が太く肉厚で食べ応えあり/ドラムスティックのような形/味がしみ込みやすくジューシー | 煮物、スープ、カレー、唐揚げ |
| 手羽中 | 手羽先と手羽元の中間/肉と皮のバランスが良く食べやすい/「フラット」とも呼ばれる |
調理の基本と下ごしらえ
こちらでは、鶏肉を美味しく料理するために、臭みをとり、やわらかく仕上げるひと工夫を紹介しますね。
- 酒や生姜を加えて臭みを抑える
- 繊維を断つ方向に切ると柔らかい
- むね肉・ささみは低温でじっくり火入れ
- 手羽や鶏ガラは、スープの出汁として大活躍
- 砂糖を少量加えると保水性が高まり、加熱してもしっとり仕上がる
鶏肉の衛生管理と調理の注意
鶏肉は新鮮で扱いやすい食材ですが、衛生管理を怠ると食中毒のリスクがあります。
美味しく安全に楽しむために、必ずこの3つを守りましょう!
⚠️ 鶏肉を扱うときの3つの基本
- 生食はしない
中心部までしっかり加熱(75℃で1分以上が目安)。生焼けの唐揚げや鶏刺しはリスク大。 - 調理器具は分ける or すぐ洗う
生肉を切った包丁・まな板で野菜や果物を切らない。使用後は洗剤+熱湯消毒が安心。 - 手洗い&保存を徹底
生肉を触ったら石けんで手洗い。保存は密閉袋や容器に入れ、冷蔵庫の一番冷える場所へ。
🍱 お弁当に使うときの注意
- 加熱後は常温に長時間放置しないこと。
- 詰めるときはしっかり冷ましてから入れると安心。
和食における代表料理

全国各地には「鶏肉が主役」の料理がたくさんありますね。ここにあげたのは、全国的に和食の定番になっているものの、ほんの一部です。
- 親子丼(東京):卵と鶏のやさしい丼。
- 筑前煮(福岡):根菜と煮合わせた祝い料理。
- 水炊き(博多):白濁スープで煮込む鍋料理。
- きりたんぽ鍋(秋田):比内地鶏の旨味が主役。
- 鶏雑煮:地域によってはお正月に登場。
鶏肉の保存と扱い方
大容量のパックで購入すれば、お得に購入できる場合があります。そんなとき、できるだけ品質を落とさず保存したいものですよね。最後まで美味しく使い切るために、これらをぜひ参考にしてみてください。
- 冷蔵:水気を拭き取り、2日以内に調理。
- 冷凍:小分けにして下味冷凍がおすすめ(下のコラム参照)。約1か月保存可能。
- 解凍:冷蔵庫で自然解凍が基本。
鶏肉と和食調味料との相性

「さしすせそ」を中心に、鶏肉はどの調味料とも相性が抜群です。組み合わせごとの特徴を知ると、味付けの幅がぐんと広がりますよ。
鶏肉×基本調味料「さしすせそ」
砂糖(さ)
- 効果:旨味を引き立て、保水性を高めてしっとり仕上がる。
- 向く料理:照り焼き、煮物、甘辛炒め
- コツ:塩より先に加えると肉がやわらかくなる。
塩(し)
- 効果:味を引き締め、素材本来の旨味を際立てる。
- 向く料理:焼き鳥(塩)、蒸し鶏、スープ
- コツ:振りすぎない。下味の段階で軽く塩をしておくと水分が均一に回りやすい。
酢(す)
- 効果:酸味でさっぱり、殺菌効果も期待できる。
- 向く料理:南蛮漬け、甘酢あん、さっぱり煮
- コツ:加熱しすぎると酸味が飛ぶので、仕上げに加えると香りが残る。
しょうゆ(せ)
- 効果:香ばしい風味とコクを与える和食の要
- 向く料理:照り焼き、煮物、親子丼
- コツ:焼き料理では最後に絡めて照りを出す。煮物は早めに加えて味を含ませる。
味噌(そ)
- 効果:発酵由来の旨味と香りで鶏肉のコクを引き立てる
- 向く料理:鶏の味噌漬け焼き、味噌鍋、炒め物
- コツ:焦げやすいので焼くときは弱火でじっくり。みりんや酒でのばすと扱いやすい
鶏肉×その他の調味料
- 酒:臭みを消して旨味を引き出す。煮物や蒸し物に必須。
- みりん:照りと甘味をつける。照り焼き・煮物に。
- だし:鶏肉の旨味に昆布やかつおの風味が重なると、上品な味わいになる。
現代的なアレンジと食べ方
鶏肉は、和食の定番だけでなく、現代のライフスタイルに合わせて新しい楽しみ方も広がっていますね。鶏肉は、ヘルシー志向や時短を重要視する現代人にはぴったりの万能食材です。
サラダチキン
コンビニの定番商品として一気に広まったのがサラダチキンです。むね肉を低温でじっくり加熱することで、パサつかずしっとりとした食感に仕上がります。
塩味やハーブ風味、カレー風味など味のバリエーションも多く、手軽にたんぱく質を補給できるのが魅力です。
鶏ハム
むね肉を砂糖や塩で下味をつけ、ラップで巻いて加熱するだけでできるのが鶏ハムです。シンプルながら保存性が高く、冷蔵庫に常備しておくとお弁当やサンドイッチにすぐ活用できます。柔らかく仕上がるので子どもから大人まで食べやすい一品です。
低温調理(真空調理)
近年注目を集めているのが、鶏肉を真空袋に入れて低温でゆっくり加熱する「低温調理」です。火を通しすぎて固くなりやすいむね肉やささみが驚くほどジューシーに仕上がり、調味料の風味もしっかり染み込みます。
ヘルシー志向の調理法
健康志向の高まりとともに、鶏肉は油を控えた調理法でも多く取り入れられています。例えば、蒸し鶏を冷やしてサラダに添えたり、鶏むね肉をヨーグルトや塩麹に漬けて焼いたりする方法は人気です。また、香味野菜や酢を使ってアクセントをつければ、さっぱりとした味わいが楽しめます。
筋トレ・ダイエット食
高たんぱく・低脂肪で知られるむね肉やささみは、ボディメイクやダイエットを意識する人に特に支持されています。茹でてストックしておけば、サラダやスープ、炒め物にすぐ加えられるので、栄養管理がしやすく続けやすいのもポイントです。
おわりに

鶏肉は、「おなじみのおかず」として私たちの台所に並んでいますが、こうして特徴を知ると、今日の献立を考えるのが少しだけ楽になりませんか?
唐揚げや親子丼のような定番から、筑前煮や水炊きのような郷土料理まで、鶏肉は「日常」と「ごちそう」の両方を担う存在。
万能食材だからこそ「今日はどの部位を、どんな味付けにしようかな?」――そんな使い方ができたらいいですよね。
\ほかの食材をもっと見る/
▼